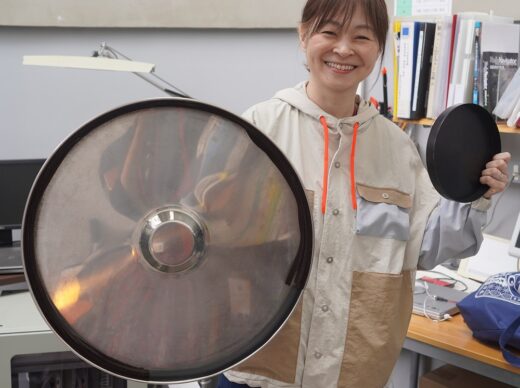研究者インタビュー|【分子レベルで生命現象の根本に迫る 】清水光弘教授(理工学部 総合理工学科 化学・生命科学コース)
おりは
みなさんこんにちは、学生サイエンスコミュニケーターの「おりは」です!
今回は、理工学部 総合理工学科 化学・生命科学コースの清水光弘 先生にインタビューしてきました。先生の研究内容や研究の面白さ、プライベートなことまで語っていただきました。
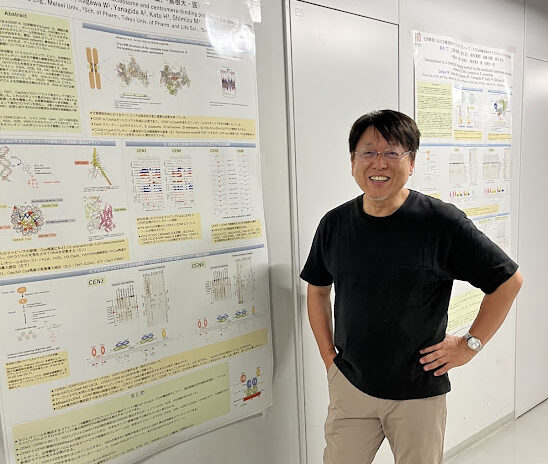
一分間チャレンジ「先生の研究を一分で紹介してください!」
【清水先生】
僕はDNAと染色体について研究をしています。人間の体を構成する1個の細胞には、約2mのDNAが直径わずか10ミクロン(0.01mm)の細胞核の中に収められています。身長よりも長いDNAが目に見えないほど小さな核に入っているわけです。
どうやってゲノムのDNAが細胞の核に納められ、また、必要なときにどのようにして遺伝情報が取り出されるのか?これが興味の根幹にあります。
染色体の基本構造はヌクレオソームと呼ばれる、ヒストンタンパク質とDNAとの複合体です。人の細胞核1個には約3000万個のヌクレオソームが入っており、遺伝子発現のプラットホームになっています。
私のラボでは、ゲノム、染色体・クロマチン、ヌクレオソーム、あとはエピジェネティクスをキーワードにして、出芽酵母をモデル生物に研究しています。
エピジェネティクスって何ですか?
【おりは】
タンパク質やDNAは誰もが聞いたことのある言葉だと思いますが、エピジェネティクスはあまり馴染みのない言葉ですね。詳しく教えてもらってもいいですか?
【清水先生】
エピジェネティクスは、DNAのG、A,T、Cといった4種類の文字(塩基)の配列だけでは決まらない遺伝の仕組みと言えます。分かりやすい例として、私たちの体は、受精卵という1個の細胞からスタートして、数十回の細胞分裂を繰り返してつくられました。その初期の細胞分裂で2個、4個、8個となり、これらは同じ性質の細胞ですが、さらに分裂を繰り返していくと、約200種類の細胞に変わり、さまざまな器官や臓器となります。
最初の受精卵のゲノムDNAがコピー(複製)されて、細胞分裂していきますので、体のすべての細胞に含まれるゲノムDNAは基本的には同じものですが、細胞の個性は異なります。
すなわち、DNAの配列だけでは説明できない遺伝子の発現調節があり、これがエピジェネティクスです。エピジェネティクスが正常に働かなくなると、ガンやいろいろな病気になると言われています。
エピジェネティクスのメカニズムに関わっているひとつは、ヌクレオソームを構成するヒストンというタンパク質ですが、ヒストンの脱アセチル化を阻害する酵素をターゲットに、実際、新薬も作られています。エピジェネティクスは大事なキーワードですね。
研究によって、将来どんなことができるようになると思いますか?
【清水先生】
僕が行っているのは基礎的な研究で、それが直ちに何かの役に立つというよりは、生命現象の根本的な疑問の解明や、分子的な理解ができるようになるのだと思います。よく言う真理の探究ですが、それが分かると何がいいかと言うと、究極的には医療につながるかも知れないということです。
例えば正常な細胞とがん細胞のような異常な細胞は違うわけですが、じゃあ何が変わったら病気になるのかというメカニズムの解明や創薬に繋がると思っています。基礎研究の重要性は、アメリカで分子生物学の基礎研究が大きく進んだ結果、遺伝子工学の発展をもたらした例でもよく分かります。
研究のここが面白い!というところを教えてください。
【清水先生】
そうですね、よく授業でも言っていますが、僕らの研究分野の分子生物学では、「大腸菌で正しいことはゾウでも正しい。」という有名な言葉があります。これを最初に読んだとき、「おぉっ」と思いました。大腸菌とゾウでは、もちろん、違うことは多いでしょうが、同じ面もたくさんあるということです。我々人間も含めて当てはまります。すべての生物に普遍的なことと、個々の生物に特異的なところを分子のレベルで解き明かすことが分子生物学の一つの魅力じゃないかなと思います。
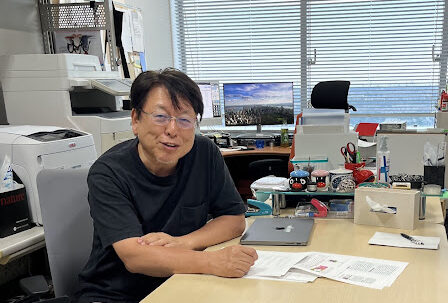
大学の先生になるまでを教えてください!
【おりは】
清水先生が中高生のころは、どんな生徒でしたか?
【清水先生】
普通の生徒でしたね。中学では卓球部に入っていて、生徒会長をやったこともあります。あとは友達とよくイタズラをして、先生に怒られたりもしましたけど、ありきたりの生徒だったと思います。
高校時代は特に何もやってなかったかな。本は適当に読んでいましたけれど、そんなにたくさん読んだ方でもないし。目の前のことに興味を持ちつつ、楽しく生きていたような気がします。
【おりは】
ちょっと意外ですね。大学の先生になられる方は中高生時代から、がっつり勉強しているのかなと思っていましたが、なんだか清水先生がより身近になった気がします。先生が今の道に進むきっかけはなんでしたか?
【清水先生】
生物の分野に進むと決めたのは大学院の終わり頃です。学部・大学院では生物物理的な研究をしていました。NMR(核磁気共鳴)装置という分析機器を使ってヒストンやDNAを調べて、それで博士論文を書きました。今も研究しているヒストンに、実は修士1年のときに出会ったのです。NMRの原理を勉強していくうちに、自分がNMRの分野で最前線の研究をすることは難しいかなと思いました。
博士課程が終わる頃、自分のやりたいことを考えて、DNA、ヒストン、ヌクレオソームをもっと研究しようと思い、分野を完全に分子生物学にシフトしました。博士の学位を取った後、アメリカに3年間行きました。大腸菌に初めて触ったのはアメリカに行ってからで、その後、出芽酵母とも出会いました。
アメリカでの研究生活が面白かったから、生物の分野で研究者になりたいと思ったのでしょうね。
【おりは】
凄い行動力ですね。やっぱり研究者になるには興味が一番大切なのでしょうか?
【清水先生】
そうですね、興味や好奇心は大切だと思います。分からないことに対して実験を組み立て、予想外の結果も含めて面白い結果が出た時のわくわくした気持ちや快感を味わうと、研究はやめられなくなりますよ。
100年後の未来はどんな風になっていると思いますか?
【おりは】
ゲノム研究者の清水先生から見て、100年後の未来で今と変わっていたり、新たにどんなことが分かるようになっていたりすると思いますか?
【清水先生】
これは難しいね。でも何か分かるとしたら、僕らの分野では、細胞の中で物質の相互作用が詳細に明らかになるんじゃないかと思います。僕らが研究しているDNAやタンパク質は、単品では機能を発揮できないんです。タンパク質がDNAに作用しないと遺伝情報は引き出せません。分子間の相互作用があって機能するわけです。
人間社会も同じで、個人ではできないことが、さまざまな人と相互作用することによって成り立っています。今後、100年とは言わないですけど、分かるとしたら一つは細胞の核の中でのさまざまな分子や物質の相互作用のネットワークです。
人のタンパク質の遺伝子数は約2万種、タンパク質の種類は約10万種と言われています。そうなると、タンパク質だけでも組み合わせの数は膨大で、そこにDNAやRNAとの相互作用、作用する時間軸も加えるとなかなかの難問だと思うんです。
細胞核の中で分子の何と何が近いとか、時間と空間で相互作用がある程度分かるかも知れないので、その辺のメカニズムがだいぶ解明されるかもしれないですね。
また、脳の記憶、考えて話したりする思考、また精神状態とかそういうのも、究極的には物質の相互作用で起こっていると思うんですけど、どういう分子がどういう風に相互作用して、私たちが楽しく感じたり、あるいは怒るのか、といったことが分かるかもしれないですね。
中高生へ伝えたいこと
【おりは】
最後に中高生へメッセージをお願いします。
【清水先生】
興味を持ったら何でもまずはやってみることだと思います、僕はそう思っています。これも授業で言いましたけど、「知識は人を自由にする」という言葉があります。
要するに、一見無駄に見えたりとか、何でこんなことやるんだろうと思ったりしたとしても、いろいろな知識をもつことによって選択肢が増えます。すなわち、人生の自由度が高くなるということです。反対語は「無知は人を奴隷にする」という言葉ですが、知らないということは、他の人や置かれている状況に支配されがちになるかも知れません。そうなると、怖いよねって話になりますので。
中高生の人には、積極的に頑張っていただければと思います。
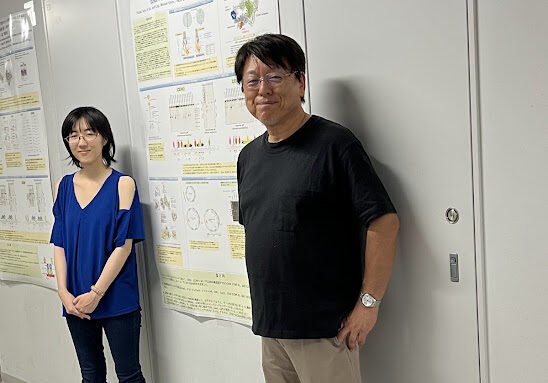
終わりに
【おりは】
今回のインタビューでは、学生が普段目にしている研究者としての一面のほかに、普段は目にすることのないちょっと意外な一面も見えてきました。
自分のことは自分が一番よく知っている、と言うこともありますが、分子生物学的に見ると実際に分かっているのはほんの一部なのかもしれません。生物は未知とロマンに溢れていて、これからどんなことが分かっていくのか楽しみです。
清水先生、ありがとうございました!
好きな分野
ひとこと
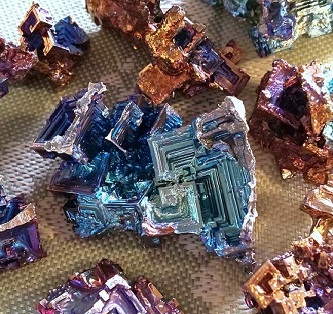
年月掲載
*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。