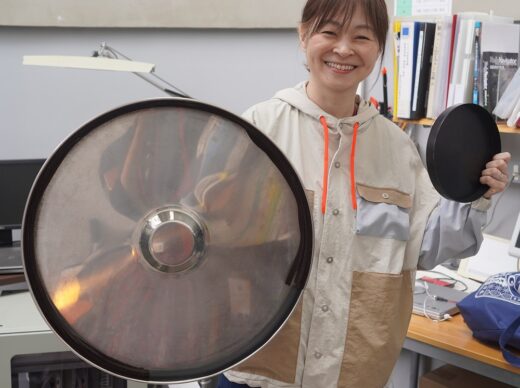無駄を出さないクリーンな燃焼技術の研究、学生はピザ窯づくりにも挑戦【理工学部 齊藤剛 教授】
おせっかいな研究広報さん
研究者インタビュー【取材:研究広報さん】

齊藤 剛 教授 (明星大学/ 理工学部 総合理工学科)
クリーンな燃焼技術の研究
─齊藤研(燃焼工学研究室)の学生は、毎年ピザ窯をつくっていますよね。楽しそうなのでいつも気になっています。今日は齊藤教授に燃焼工学とピザ窯の話を聞きたいと思います。
齊藤教授:興味を持っていただきありがとうございます。なんでも聞いてください!
─はじめに、齊藤教授の研究について簡単に教えてもらいたいです。
齊藤教授:はい。私の専門は熱工学です。環境にローインパクトで高効率なエンジンの開発に向けて燃焼技術の面からアプローチする、という研究をメインでやっています。
─クリーンな燃焼技術の開発ですね!
齊藤教授:そうです。特にレーザー光を焦点に集光しブレイクダウンを起こし、生成されたプラズマにより着火させる「レーザーブレイクダウン着火法」という着火方があるのですが、それを実際のエンジンに応用する研究しています。
「レーザーブレイクダウン着火法」×エンジン
─具体的にはどのような研究なのでしょうか。エンジンというのは車のエンジンですか?
齊藤教授:そうです。車や草刈り機、あとは発電機のエンジンをイメージしてもらえたらわかりやすいでしょうか。これらの今動いているエンジンに「レーザーブレイクダウン着火法」を適応した場合の出力などを調べています。

レーザー着火式エンジン
─ふむふむ。エンジンにその着火法が適応できた場合、どのようないいことがあるのでしょうか?
齊藤教授:「レーザーブレイクダウン着火法」は、まず第一に火をつける能力が大きいというところが特徴です。さらに、エンジンの中を分析できるというのがあります。温度や燃料の濃度などがわかるので、なにが起きているのかを確認しながら運転できるのです。
─エンジンを分析・・・ですか?
齊藤教授:自動車を運転する時のエンジンは「エンジンをかける」「エンジンを切る」ですよね。実際のエンジンに「レーザーブレイクダウン着火法」を応用できたら、分析によって、動力が失われる前に発見したり微調整したりが可能になります。
─なるほど!自動車のエンジンでいうと、何が起きたのかわからないまま突然エンストして事故が起こる、ということがあると思いますが、それが防げるということでしょうか?
齊藤教授:そうなんです。例えばヘリコプターによるアルプスの山岳救助のような場合、高高度を飛行することになります。アルプスのような空気が薄い場所だと、地上での想定と大きく変わることがあり、実際に飛行してみないと極限がわからないという問題があります。
─ふむふむ。改めて考えるとエンジンの状態がわからないというのは危ないのですね。「レーザーブレイクダウン着火法」の技術により分析可能なエンジンが開発されれば、予期せぬ事故がかなり減るのではないでしょうか。
学部を越えた学びの機会
─燃焼工学研究室を選ぶ学生の興味関心は、やはりエンジンでしょうか?
齊藤教授:エンジンを学びたい学生は多いですね。あとは環境問題に関心がある学生も多いです。
─社会課題に関心の強い学生が多い印象がありますね。SATOYAMAプロジェクトの話題になりますが、研究室の学生が毎年ピザ窯をつくっている話と、学内にある膨大な落ち葉を利用してペレットをつくっている活動がとても気になっています。ぜひ研究室の活動も教えてください。

燃焼工学研究室の学生と齊藤教授
自作のピザ窯の前で。
齊藤教授:学生たちが改良を重ねている移動式のピザ窯は、昨年のものが3代目だったのですが、残念なことに壊れてしまいました。ピザ窯はコンクリートで作っているので、なぜ壊れてしまったのか検証するため、建築学部の鱒沢曜准教授に相談に行きました。ちなみに、鱒沢准教授の研究室の学生がピザ窯を卒研テーマに選んだということも聞きましたよ。
─コンクリート構造は鱒沢准教授のご専門ですものね。学部を越えた学部横断型の学び(*1)があるところが、明星大学のおもしろいところですよね!明星大学は教員同士のつながりも多いという印象です。
齊藤教授:最初にピザ窯をつくることになった時も、建築学部の年縄教授に聞きにいきましたね。
─建築学部の年縄教授は自宅にピザ窯をつくったのですよね。私も年縄教授に、効率よく焼くピザ窯の構造があるのですか?と聞いたら、アーチ構造やドーム構造によって壁からの「ふく射熱」を効率的に集めることがポイントなのだと、話を聞きました。

年縄教授の自宅のピザ窯
齊藤教授:そうなのです。大きな改良が必要になりますが、学生たちのピザ窯も、壁からの「ふく射熱」を利用できる形状にしていくのが、昨今の目標ですね。

─ピザを焼くためのエネルギーも学生たちがつくっているのですよね?すべて自作で、学内で完結しているのがおもしろいです。
齊藤教授:明星大学は自然が多く、落ち葉や丸太などの自然エネルギーも豊富にあります。SATOYAMAプロジェクトでは、それらを生かせる研究をしていました。
─具体的にどのような自然エネルギーをつくっているのでしょうか?
齊藤教授:学生がピザ窯のためにつくっているのは、薪です。薪で、120秒ほどの短時間で焼き上げるので、ピザの外側はカリカリ、内側はふっくらしていますね。
─ほう。専門店のピザがおいしいのも、ピザ窯で短時間で焼き上げるからなんですね。学生が薪をつくるとのことですが、丸太を乾燥させるのにはかなりの時間がかかりますよね。
齊藤教授:はい。里山で間伐した丸太を1年間倉庫で乾燥させてつくります。時間がかかるので、来年の後輩のために代々引き継ぎながら行っていて、このプロジェクトは7年目です。
─そんなに長く続いている活動だったのですね!齊藤研の学生たちは、例年学園祭でピザを出店していますよね。学部を越えて評判がよいので今後も続いてほしいです。

SATOYAMAプロジェクトの
ワークショップの参加者に
学生が焼き立てピザを提供。
企画者のデザイン学部の萩原修教授と。
炭素循環型社会を目指す
─齊藤教授が研究開発している、落ち葉ペレットのお話もききたいです。
齊藤教授:落ち葉を使ったバイオ燃料は、化石燃料に比べて、温室効果ガスの排出や大気汚染の削減になりますからね。落ち葉でつくったペレットであっても、木質と同程度の発熱量を出すことができるのですよ。
─街中では落ち葉はゴミになってしまいますから、それをエネルギーに変えることができたらすごいですよね!落ち葉からどのようにつくるのでしょうか?
齊藤教授:落ち葉を乾燥させ、破砕したものの水分量を調整しながら圧縮させてつくります。制作のための治具の設計から制作までもやっています。

自作の落ち葉ペレット製作治具
(シリンダの中に破砕した落ち葉を入れ、ピストンで力をかけて押し固める)
─落ち葉ペレットをつくるうえで難しいところがあるのでしょうか?
齊藤教授:一番の問題は強度なのです。落ち葉ペレットはそのままでは脆いので、硬度を明らかにして運搬に耐えられるほどの強度を増やす工夫について研究しています。
─なるほど。流通にあたり保管や運搬などを考えると、強度が重要ですものね。
齊藤教授:強度も問題がクリアできれば、落ち葉ブリケットや人工薪への応用もできると思っています。炭素循環型社会を目指して研究しています。

条件を変えて制作した
落ち葉ペレット(3種類)
左から
①落ち葉に水を加え加熱し圧縮したもの
②落ち葉を圧縮(弱)だけのもの
③落ち葉を圧縮(強)だけのもの
コージェネレーションシステムの開発で
甘いイチゴを育てる?
─齊藤教授が研究されている木質ペレットを使った「コージェネレーションシステムの開発」についても教えてほしいです。
齊藤教授:コージェネレーション(Cogeneration)は、簡単に言えば「ひとつの燃料から、電気と熱を同時に作り出すシステム」です。例えば、発電するときに出る排熱(ムダになりがちな熱)があるのですが、これを給湯や暖房などに再利用する、とかです。
─エネルギーの無駄が減る、という事ですね。具体的な構想もあるのでしょうか?
齊藤教授:今考えているのは、ビニールハウスでの活用です。イチゴやメロンなどの作物には人工的に二酸化炭素(CO₂)を供給しているのを知っていますか?
─えっと、ビニールハウス内で植物にCO₂ を吸わせているということでしょうか?なんのために?
齊藤教授:CO₂の供給は植物の光合成を促進し、収穫量や品質を向上させるための技術で、果物が甘くなったり、大きく育ったりするんですよ。
─知りませんでした。どのようにCO₂ を供給するのでしょうか?
齊藤教授:多くは石油ボイラーなど、化石燃料を燃やして発生させたり、CO₂ボンベを買ってビニールハウス内に充満させたりですね。ビニールハウス内でろうそくを焚くというのは、昔からよくある光景なのですよ。
─知りませんでした。燃焼の際に出るCO₂を、ハウス内に充満させるということですね?化石燃料を燃やしたり、わざわざボンベを買ったりしなくても、木質ペレットを作って使えればエコでいいですね。
齊藤教授:はい。その通りです。この木質ペレットも農業残渣(ざんさ)が使えたらいいと思っているのです。イチゴで言うと、イチゴだけ収穫して、茎や葉、ヘタなどは捨てますよね。ゴミとなるものを活用してペレットがつくれたらいいと思っているのです。
─わぁ、それはすごい。エネルギーの無駄も減って、ゴミも減る。よいことだらけですね。ピザ窯の話から繋がりますが、齊藤教授の研究はまさに「自給自足型」のおもしろさがありますね。海外から輸入したり取り寄せたりしたものを使うという考えではなく、今すでにある、捨ててしまうものに目を向けて、新たな価値を生み出すというのがとても魅力的です。
齊藤教授:エネルギーを無駄なく使う「省エネルギーな燃焼技術」で、CO₂排出も上手に利用できれば、持続可能な社会に貢献できると思っています。
─«レーザーブレイクダウン着火法を応用したエンジンで草刈り機を動かし、農業残渣で電気と熱を同時に作り出し、燃焼で出たCO₂も無駄にはしない。»
齊藤教授の研究が最終的にすべてつながっていて循環しているのがとても興味深いです。
「明星 SATOYAMAプロジェクト」は学部横断型のクロッシング・プロジェクト
*1 ワンキャンパスに9学部1学環が集結した総合大学である明星大学ならではの取り込みとして、幅広い学部の教員や学生が、それぞれの視点や専門性を持ち寄り、掛け合わせながら考える、学部横断型のクロッシング・プロジェクトがあります。
ひとこと

年月掲載
*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。