
研究前にひと休み #03
環境にやさしい有機合成の鍵は酵素の構造にあり!
冨宿 賢一
理工学部 総合理工学科
教授 /博士(理学)
生物機能有機化学研究室
このコラムは冨宿教授に化学と生命科学をわかりやすく教えてもらう連載の第3回目です。前回は有機合成(古くからの化学工業)が直面している環境課題について教えてもらいました。
有機合成は環境への負荷が大きい点が課題です。その点、酵素を有機合成に利用することがどれほど「環境にやさしく持続成長可能(グリーンサスティナブルケミストリー)」な技術なのか、わかってきました!
そうですね。今回は酵素を使った有機合成の利点をもう少し説明しましょう。
「環境にやさしい」以外もあるのでしょうか?
はい。もう一つの大きな特徴として立体構造の識別の話をしましょう。香料や化粧品、農薬、医薬品など有機化合物の多くは、「右手と左手」のように、鏡像関係にあるけれど互いに重ね合わせることができない鏡像異性体(エナンチオマー)の存在する分子です。
このことを医薬品で例えると、「右手型」だけが望む薬効を示し、「左手型」は作用を示さないor有害、というようなことが起こり得ます。
なるほど!
通常の化学合成では、両方のエナンチオマーが等しく混ざった混合物(ラセミ体)として生成物を生じるので、これらを分けることは非常に難しいんです。
一方で、酵素はこれらのエナンチオマーを「右手型」、「左手型」というように区別することができます。
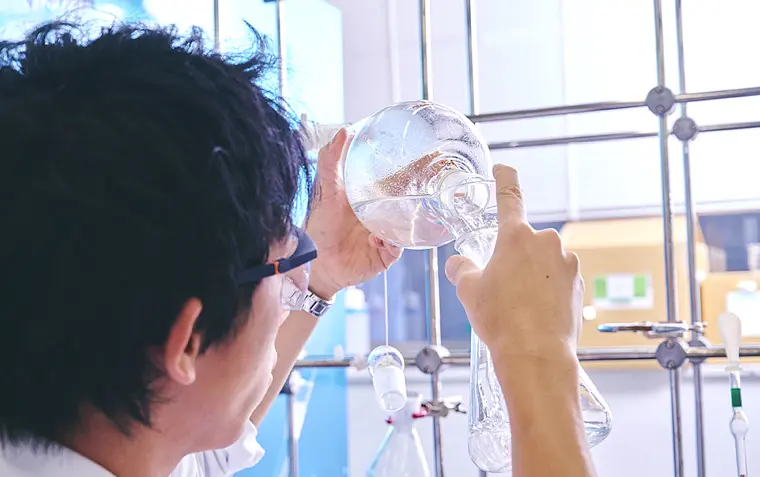
どうしてですか?
実は酵素には左手型(L-アミノ酸)しかないので*、作用する分子の立体的な構造のわずかな違いですら見分けることができます。つまり、ラセミ体の分子であっても、左手型からなる酵素なら、両方を区別することが可能です。
*鏡像関係にある右手型はD-アミノ酸
ふむふむ。その立体的な構造を識別する能力を有機合成に利用するんですね!!
そうです! ラセミ体の生成物から両方のエナンチオマーを区別して分ける「光学分割」が可能です。それだけでなく、予め化学反応の中に酵素を触媒として組み込むと、不要なエナンチオマーを生じずに、欲しいエナンチオマーだけを作る「不斉合成(ふせいごうせい)」が可能になります。
ずいぶん合理的ですね!
エナンチオマーを作り分けること自体は、複雑な触媒を重金属試薬や有機溶媒と組み合わせて使っても実現可能なのですが、環境への負荷や必要とするエネルギーが大きいので、酵素を利用する方が優れていますよね。
グリーンサスティナブルケミストリーは、化学分野の重要な潮流ですからね。次回は酵素を使った有機合成で実際にどのようなものが作れるのか教えて欲しいです。
冨宿 賢一
理工学部 総合理工学科
教授 /博士(理学)
生物機能有機化学研究室

専門分野
生物有機化学、応用微生物学
キーワード
生体触媒、酵素、微生物、光学活性物質、生物活性物質、不斉合成、ドミノ反応
研究室HP
生物機能有機化学研究室教員情報
明星大学教員情報 冨宿 賢一生物機能有機化学研究室では、化学と生命科学、両分野の知識や技術を学びながら、「酵素」の特徴を最大限に活かして、香料や化粧品、農薬、医薬品など役に立つ物質の「有機合成」に取り組んでいます。
2025年9月掲載
*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。





